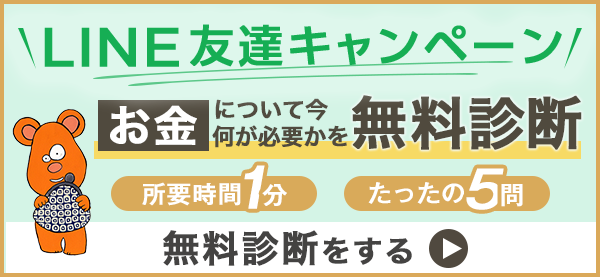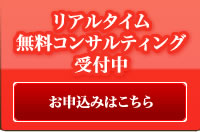資産運用初心者が陥る、証券会社や銀行で「任せているから安心」という勘違い
公開日:
:
最終更新日:2016/01/18
資産運用の基礎、Q&A、基礎用語
こんにちは、K2 Investment 投資アドバイザーの眞原です。
今回は資産運用の基礎シリーズ。
相続で引き継いだ株式や投資信託、債券を保有しているけれど、自分は全くの(資産運用の)素人で金融の知識も無いので「証券マンにお任せしています」。「元本を減らしたくない」とは伝えているものの、証券マンに〇〇という投資信託を勧められているが投資して良いかの判断が付かない。
はい、これはよくあるパターンです。
今の40代後半〜50代の方で「相続で大金を引き継いだ」、「祖父や祖母が保有している投資信託を相続した」という話が多くあります(そういう資産移転の時期というのは確かなので、信託銀行や証券会社は自社から資産を逃すまいとファンドラップなどで必死に営業攻勢をかけているのですが)。
※ベンチマークインデックスに負けていると評判の野村ファンドラップ(バリュー・プログラム)/野村證券
さて、ここで冷静に考えると上で確認したような悩みに対する回答としては、
・金融知識や経験が無いのであれば、勉強しながら実践しましょう。 ・日本の投資金融商品において資産運用において元本を減らしたくないのであれば、株式や投資信託は投資してはいけません。
・「証券マン(や銀行員)に任せる」という、自己責任ではなく他者責任にしているのはもってのほか。
ということです。
・金融知識や経験が無いのであれば、勉強しながら実践しましょう。
相続で突如資産を受け継いだ場合「何にも分からないままなのですが!」というのが正直なところでしょう。
「急に」資産が増えるのですから、それまでそのような資産を持ったことがない以上はどうして良いか分からない
→だから「証券マンや銀行員の言うとおりにするのが正しい(任せていれば安心)」という思考パターンになるのですが、私からすれば完全に間違いだと言えます。
(ちなみに私は自分の両親には、口座を持っている銀行員&証券マンの資産運用話は全く聞かなくて良いと言っています)
もちろんある程度、資産運用や金融経済を分かっている人は、自分で資産運用をしているので(苦笑)。
「資産運用」は、いわば「勉強(知識+経験)」の真剣勝負です。
株式、為替、債券のマーケットではオフショアファンド(ヘッジファンド)マネージャー然り、年金基金のファンドマネージャー、投資信託(ミューチャル・ファンド)マネージャー、証券マンやアナリスト、デイトレーダーといった「しっかり勉強をして本気で儲けたい、儲けなければいけない」多数のプレイヤーの思惑や行動が渦巻いています。
例えば、全く勉強(基礎知識)もなく、試験会場で試験を受けろと言われて、まともな点数が取れないのと同じで、知識武装なくして資産運用を始めるのは単に損をするか、もしくは運良く儲かるかの運任せでしかないでしょう。
だから若い頃から「資産運用は私には無関係」ではなく、勉強してくださいということです。
勉強せずして「簡単に資産が増える」というのは大きな間違いであって、勉強したくなければ資産運用はすべきではありませんし、相続した運用資産は早々に売却して現金化すべきです(きっと現金化しても、その大金が入った銀行口座の銀行員が同じようにセールスしてくる=現金では置いておけないような環境になるのでしょうけれど・・・。)
とはいえ、単に勉強だけすれば良いのかというとそういう訳ではない理由は、こちらの記事に譲るとします・・・。
※資産運用は実践が先で、経済金融知識は同時に学ぶもの。2度と戻らぬ時間を無駄にしないための考え方/資産運用の基礎
・日本の投資金融商品において資産運用において元本を減らしたくないのであれば、株式や投資信託は投資してはいけません。
「資産運用」=「リスク1〜100%」です。つまり「リスクゼロ=元本保証」は絶対にあり得ません(元本確保運用はありえます)。
なので、例えば「元本を減らしたくないのに、大きなリターンを得たい」というのは、完全に矛盾しているし(悪く言えば、完全に欲の皮が突っ張っている)あり得ない話です。典型的な詐欺がこういうのを謳っていますね。例えば「元本保証で、高利回り!」など。
資産運用において「元本保証」はあり得ません。
もし元本保証を希望するのであれば、相続した資産(株式、投資信託)は早々に売却して現金化するしかありません。
資産運用では、リスク(上下のブレ)があるからリターン(銀行で預けている以上のリターン)を得られるのです。
※資産運用初心者が抱える、5つのあり得ない誤った考え方について(その1.)/資産運用の基礎
・「証券マン(や銀行員)に任せる」という、自己責任ではなく他者責任にしているのはもってのほか。
良くも悪くも「資産運用」は(フェアな情報が開示されている上で自分で最終的な選択をしている限り)「自己責任」です。
「証券マンに勧めらるがままに・・・」、「よく分からないまま・・・」、「こんなことは聞いていなかった・・・」と投資しているものがマイナスになると必ずこういう投資家がいます。
が、
「最後に投資をするという決断をしたのは自分自身です」というのが現実です。
もちろん、証券マンや銀行員が開示しなければいけない情報を開示しているというのが大前提ですが、投資家自身にも「分からないことを聞く権利や聞く時間」はある訳です。その自助努力を行わずして「言われるがまま、証券マンを信じて、任せている」というのは大きな間違いです。
(フェアな情報開示の上では)、証券マン(銀行員)が何と言おうと、最後の決断(投資判断)をした個人投資家による「自己責任」(クーリングオフはありません)です。
また「任せている」というのは日本の証券会社や銀行ではあり得ません(一任勘定はないため)。つまり投資家は彼らに「任せている気になっている」というのが正しいと思います。
「証券マンの仕事」はセールス(営業、販売)なので、販売をして手数料を上げるというのが彼らの真っ当な仕事です。なので個人投資家が仮に「任せている」と勘違いをしていると、彼らは「この投資家はセールスして欲しいのだ」ということになります。
※営業を受けたがる受動的な投資家(消費家)と自分で考える能動的な投資家の違い/資産運用の基礎
「安心」という感情に左右されないこと
あの大手銀行員が言うから「安心」、証券マンが熱心だから「信用できる」というのは主観でしかありません。もちろん、人を信じる面では非常に大事な要素です。が本来資産運用においては「パフォーマンスが全て」です。
上で確認したように自己責任を下に、自分で調べ、学び、行動することで、何も分からず相続で引き継いだ大事な資産を守りながら中長期で資産運用できるというのは言うまでもなく可能です。
また資産運用で増やしていかない限り、厳しい未来(老後)が待っているというのも間違いない日本社会でしょう。
※特に40代以下世代で年金制度を信じられない人が老後資金を備えた方が良い理由〜GPIF(年金基金)大損の可能性〜/みんなの年金問題
海外積立投資入門書(マニュアル)を
無料進呈します
毎月の余剰資金から少額ずつ(100ドルから)の積立をしていくことで、ドルコスト平均法と複利運用を使った資産形成をすることができます。
海外積立投資には以下の4つの種類があります。
- 最高5%上乗せボーナスを最初にもらった上で、200本のオフショアファンドで積立
- 10年後(満期)に100%の元本確保をした上で、S&P500で積立
- 15年後(満期)に140%の元本確保をした上で、S&P500で積立
- 20年後(満期)に160%の元本確保をした上で、S&P500で積立
関連記事
-

-
国債価格と金利の関係性(逆相関)
こんにちは、眞原です。 今回は「債券(国債)価格と金利」についての基礎の基礎。 とはいえ
-

-
野村證券から投資信託(米国バリュー・ストラテジー・ファンド Aコース/Bコース)を勧められています。
こんにちは、投資アドバイザーの眞原です。 今回はQ&Aです。 それでは早速みてい
-

-
過剰に求める日本社会と完璧なモノは存在しないという事実
こんにちは、投資アドバイザーの真原です。 久しぶりに日本に帰国すると、いい面と悪い面がクッキリ
-
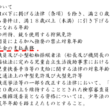
-
【年金問題】今後18歳の成人からも年金徴収を行い、年金支給は75歳からという日本の年金制度へ(自己準備で年金プラスアルファ形成を!)
こんにちは、眞原です。 今回は誰もがいつか関わってくる「退職後/高齢者になった時のお話(年金制
-
」について-110x110.png)
-
人には聞けないし、学校でも習わないけど、みんなが困っている「お金(年金準備、教育資金確保、資産運用、相続対策)」について
こんにちは、投資アドバイザーの眞原です。 今回は誰にでも当てはまる「お金全般(年金準備、教育資
-

-
「アジア好利回りリート・ファンドの分配金」について
こんにちは、K2 Investment 投資アドバイザーの眞原です。 今回はQ&A形式
-

-
国(政府)に依存してツベコベ言い続ける日本人の自己責任の欠如(=金融教育が行き届かない要因)
こんにちは、眞原です。 今回は私のふっと想うシリーズ。 よく巷で・・・、 ”日本っ
-

-
【資産運用基礎】誰でも,ゼロから始めて,中長期で資産形成できる海外積立投資(リスク別3つの選択肢)
こんにちは、眞原です。 今回は、資産運用基礎、これから資産形成をしていきたい人向けの情報です。
-

-
資産運用で放りっぱなしはあり得ない(利益確定や損切り)
こんにちは、K2 Investment 投資アドバイザーの眞原です。 今回は個人投資家の「利益確定
-

-
富裕層もサラリーマンもそれぞれの保有資産別の資産運用方法
こんにちは、K2 Investment 投資アドバイザーの眞原です。 今回は資産運用初心者から