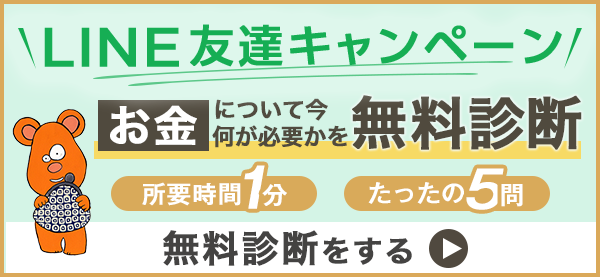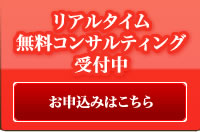高齢社会が日本経済を駄目にするかもしれない光景
公開日:
:
最終更新日:2021/02/09
気になるホットニュース(妄想・制度・規制)
こんにちは、眞原です。
今日は、ふっと感じたシリーズ。
恐らく、済んでいる地域や職種、年齢などによって大きく「高齢社会」を捉える感じ方が違うと思いますが・・・、私が主観的に思うことを書いてみたいと思います。
結論から言うと、
高齢社会が、日本経済を(スピードの面で)駄目にするかも知れない・・・
です。
※あ、決して「高齢者(や年長者)を批判している訳ではない」ので冒頭で断っておきます(むしろ、私はおばあっちゃん子で育っていますので・・・)。
ただ、私はそもそも年齢は単なるラベルにしか過ぎないという考え方です・・・。
年長者を敬う理由の1つとして「経験値の差で比較する」という考え方の人に出会うことがありますが、年上でも年下でも「経験値は人それぞれで、それを比較して優劣を付ける事自体がナンセンス」だと私はいつも感じてしまうのでこれには全く賛成できません。
年齢問わず、敬える人は沢山いるわけですので(儒教思想を押し付けないで欲しいなとつくづく思います)。
さて、日本はまさに「高齢社会のパイオニア国」です。
人間誰しも、生まれればいつかは老いて死んでしまうので、そうこう言っている私も長生きできれば、すぐにでも「高齢者扱い」される日がやってきます。
そんな「高齢社会代表日本」は、世界中の国々から「注目」されています、反面教師的に。特に中国もそのうち高齢社会化が差し迫って来るので日本を手本にしている面は往々にしてあるでしょう。
そんな中で私が感じた今後の日本社会&経済における「高齢社会」のネガティブ面になるのでは?という危惧を書いてみます。
企業は(特に上場企業は!)利益を最大限追求する
その前に・・・一般的に、企業は「利益を上げるのが目標」です。
サービスの対価として、利益を上げて、結果(=もしくは鶏卵的に「世の中が良くなっていく」)というサイクルです。
まして、上場企業(public companies)においては、当然「株主(ステークホルダー)の為に利益を上げなければいけません」。
ということは、そういう企業に勤める従業員は1人1人の1日=毎日の持ち時間を有効活用して(=単純に1日8時間労働として)、提供するサービスの対価を得るないし先行投資的で利益を上げる仕掛けや仕組みを作っていくということがその企業の利益ひいては将来の存続に影響を与えます。
さて、そんな大前提の中、名前を上げますが「郵便局(日本郵政グループ)」で気づいたことを・・・。
その企業の成り立ちからか、大体どこの郵便局でも「ご高齢」と思しき方々が沢山来ているのを目にすることが出来る場所の1つです。
「年金受取制度」があるからというのも1つの理由・・・。
誰でも感じることですが、歳を重ねるに連れて、体力が落ちていく、目が見えにくくなる、歩行が困難になる、長く立っているのが辛い、耳が遠くなる、理解力が遅くなる(聞きなれないトレンドのキーワードは分からない)、など様々な肉体的そして精神的にどうしようもない事象が生じます(=老い)。
それは当然です、それが歳を重ねること=生きているということなのですから。
ただ、それをいち企業のサービスや企業活動、日本経済を考える時に、この「高齢者の行動」が巡り巡って多大なネガティブな影響を与えるのでは?と勝手に妄想しています。
スローと繰り返しと長居
郵便局での光景がまさに今後の日本経済の象徴になっていくのでは?(自分も高齢者になった時にも同じことをしているのでは?)と思ったのが、
窓口で、あれこれ聞いて、繰り返しては、長居する高齢者の姿
です。
時刻は郵便局も忙殺時間となるであろう昼時間〜夕方にかけて、窓口は全部でたった4つ。
にも関わらず、1つは従業員が他の事務作業で対応できずCloseということは、3つの窓口がフル稼働。
それでもピーク時なため、並ぶ人の方が圧倒的に増え、10人近くが常時立ってまっている状態となっていました。
それもそのはず、本来はフル稼働をして「お客さんにサービス提供をする回転数を殖やす(=サービス提供=利益)」べきにも関わらず、3つの窓口のうち1つは、ご高齢の方がひたすら従業員に「話かけ続けている状況(=明らかに何かのサービスを提供されたいというような話)」ではなく、「おしゃべりしに来ている」という様子(窓口の後ろではその窓口が開くのを待っている行列ができているにも関わらず・・・)。
さらにもう1つの窓口では、耳がご不自由と思しき方が、なんどもなんども従業員の話を聞き返して繰り返し、結果10分以上も窓口をジャック・・・したにも関わらず、最終的は郵便局ではできないサービスだったという話だったよう。
もっと早く理解されてスピード感があれば、きっとその10分間で行列で待っている40代以下であろう若い世代(単に切手を買ったり、ゆうパックやEMS提出だけのために10分も20分も並んでいる人たち)にささっとサービス提供ができたであろうに・・・。
そして、さらに大丈夫か?と感じたのは、職員もやや年配で、高齢のお客さんと意気投合して完全に「世間話的になっている」状況を見た時・・・。
確かにお客さんに対する「人情」や「会話」は、ビジネス、とりわけサービス業や接客、営業において大事です。
ただそれでも「その従業員が働いている時間」は、実に代えがたい利益やサービスを生み出す、維持する大事なリソースです。
もしかしたら、窓口で世間話をしているご高齢者へのサービス提供ではなく、行列で立って待っている40代のその時間を有効活用できるようなサービス提供ができていれば、もしかしたらその40代の方は早く仕事に戻って、より自分の会社やビジネスのスピードを上げらるのかも知れない、など・・・。
特にゆうちょ(郵便局)を見ていると、1人のご高齢の方にサービス提供するのと、現役バリバリで働く人に対応するのでは「スピード」が違います。
サービス提供者:若者
サービス受益者:高齢者
なので、若者のスピード感に高齢者が合わせることは実質的に厳しくなり、結果高齢者の方のスピード感に合わせてサービス提供がなされていく構図。
ということは、今後も高齢化の波が押し寄せる中で「高齢者への1つのサービス提供時間が伸びる(=聞き取れない、なかなか理解されない、忘れる、メモを取る時間などなど)」結果、企業のスピード感も鈍ってきて、全体が「遅くなる」
と思うのです。
それば巡り巡って、日本経済(特に都市圏経済から)を駄目にしていくのではという危惧を感じます。
ますます「遅くなるであろう日本社会&経済&企業活動」において、企業側のサービス提供方法、内容が大いに見直されていくに違いありません。
そして、私たちが高齢者になる頃には、きっとその時の若者から「遅いな−、もっと早くしろよー」と思われているのでしょう・・・。
若者 対 高齢者という構図にはなって欲しくないなー。
海外積立投資入門書(マニュアル)を
無料進呈します
毎月の余剰資金から少額ずつ(100ドルから)の積立をしていくことで、ドルコスト平均法と複利運用を使った資産形成をすることができます。
海外積立投資には以下の4つの種類があります。
- 最高5%上乗せボーナスを最初にもらった上で、200本のオフショアファンドで積立
- 10年後(満期)に100%の元本確保をした上で、S&P500で積立
- 15年後(満期)に140%の元本確保をした上で、S&P500で積立
- 20年後(満期)に160%の元本確保をした上で、S&P500で積立
関連記事
-

-
2016年導入(2015年10月通知)マイナンバー制度への懸念〜不倫SNSのアシュレイ・マディソン個人情報流出から考える〜
こんにちは、K2 Investment 投資アドバイザーの眞原です。 今回は、番号通知まであと
-
6-110x110.png)
-
今のドル円は買い場?年内の米国利上げはカウントダウン!円安ドル高への備えを!(8/26 FRBイエレン議長のジャクソンホール講演まとめ)
こんにちは、K2 Investment 投資アドバイザーの眞原です。 今回は「為替(USD/J
-

-
2017年富裕層資産規模でアジアが西欧を抜く見込み
こんにちは、眞原です。 BCGグループ(ボストン・コンサルティング・グループ)が発表したレポー
-

-
【富裕層情報】富裕層向け贅沢品価格が上昇中!過去10年最も値上がりしているモノは??〜 The Wealth report 2019 – Knight Frank 〜
こんにちは、眞原です。 今回は、富裕層のアセットアロケーション情報です。 英国のグローバ
-

-
【経済基礎】「良いインフレ(物価上昇)」と「悪いインフレ(物価上昇)」、日本はどっちや?
こんにちは、眞原です。 今回は、経済基礎(資産運用の基礎)について。 ”皆さん、インフレ
-
は再延期らしい(日本の財政問題と高齢者やこれからの若者の年金はいかに)-110x110.png)
-
どうやら消費増税(8%→10%)決定は再延期??(日本の財政問題と高齢者やこれからの若者の年金はいかに!?)
こんにちは、K2 Investment 投資アドバイザーの眞原です。 伊勢志摩サミットが閉幕し
-

-
【為替】2018年以降はぐんぐん「円安(円の価値目減り)」に!?「壮大な社会実験」の先にあるものは資産課税?
こんにちは、眞原です。 今回は、為替事情と私の誇大妄想について。 日本時間の明日の早朝(
-
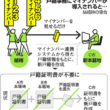
-
婚姻届やパスポート発給にもマイナンバーが必要に?
こんにちは、眞原です。 今回は日本在住者(日本に住所がある人)すべての人に関連する「マイナンバ
-
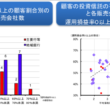
-
【投資信託(ミューチャル・ファンド)】金融庁、投信販売で「3つの共通指標」導入へ(社会主義国的な日本の金融事情)
こんにちは、眞原です。 今回は、日本の投資信託(ミューチャル・ファンド)で資産運用をしている個